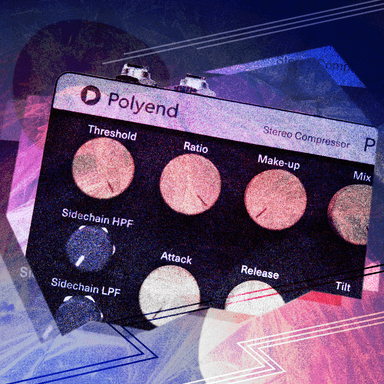アナログ・シンセサイザーの音作り ~Minimoogを題材に~
シンセサイザーで音作りをしていますか? 現在のシンセサイザーはソフトウェアが主流ですので、音色のプリセットを選ぶだけ、という人も多いかもしれません。GUI上にはツマミやスイッチが並んでいて、それらを駆使して音作りをすることができますが、実機を触ったことがないとイマイチやり方が分からない⋯⋯。でも心配はいりません。実は、シンセサイザー、特にアナログ・シンセの音作りの基本構造はとてもシンプルで、パーツごとの役割を理解すれば、すぐに自分だけの音を作り出せるようになります。
ここでは、アナログ・シンセの代表機種である MOOG Minimoog Model D を例に取りながら、音作りの基本を解説します。ここでシンセサイズの基礎知識を身につけ、自分の使っているシンセの音作りにトライしてみましょう。ちなみに Minimoog は1970年代に登場したモノフォニック(単音)のアナログ・シンセで、その太く存在感のある音は今でも多くのミュージシャンに愛用されています。
シンセサイザーの音作りの基本構造
アナログ・シンセの音作りは、大まかに次の5つのセクションに分かれています:
- オシレーター(VCO:Voltage Controlled Oscillator)
- ミキサー(Mixer)
- フィルター(VCF:Voltage Controlled Filter)
- アンプ(VCA:Voltage Controlled Amplifier)
- エンベロープ(ADSR)とモジュレーション
Minimoog ではこれらすべてが直感的なパネルで操作できるため、音の流れと変化を目で見ながら理解できるのです。今回は、シンセ・リード、シンセ・ベースの音作りを目指して、以下より、機能と音作りに関して、順番に解説していきましょう。
1. オシレーター(VCO) – 音の素材を選ぶ
音作りの最初のステップは“音の素材”=(波形)を選ぶことです。どのシンセにも、オシレーターと呼ばれるセクションに波形が用意されています。Minimoog では、”OSCILLATOR BANK”。3つのオシレーターを備えており、それぞれ異なる波形を選べます。波形によって音のキャラクターが変わるのですが、Minimoog で選べる波形は以下です。
- ノコギリ波(Sawtooth):倍音が豊かで、リードやベース、分厚いブラス系に向いています。
- 三角波(Triangle):柔らかく落ち着いた音。あまり派手ではないですが、丸みのある音でフルートのような音を作ることに適しています。
- 三角波 / 鋸歯状波:三角波とノコギリ波のハイブリッド波形で、三角波よりも倍音が多く、抜けの良い音を作ることができます。
- パルス波 / 矩形波(Pulse/Square):倍音成分が上下の幅の比で変化し、上下の幅が同じ状態の波形を矩形波と呼びます。倍音の音量は三角波よりも大きく、弦楽器系の音作りの出発点に使われます。パルス幅が広くなると、異なる倍音となり、オーボエやリード音などに向いた音が作れます。
Minimoog の3つのオシレーターは、それぞれ6種類の波形を選ぶことができるのですが、まず最初はオシレーター1つだけを使って、波形を変えながら音の変化を聴き比べることをおすすめします。ちなみに”OSCILLATOR BANK”の左側にある“RANGE”ツマミは、5オクターブで音の高さを選択でき、真ん中のオシレーター2と3に搭載された“FREQUENCY”ツマミは、オシレーター1とのピッチの差を作り、デチューンさせることが可能となっています。
2. ミキサー – 音を混ぜる
オシレーターで波形を選んだら、3つのオシレーターをどのような音量バランスでミックスするかを設定するのがミキサー・セクション(“MIXER”)。ここではノイズ(ホワイトノイズやピンクノイズ)を加えることもできます。Minimoog は音の流れを左から右に確認できるので、3つの VOLUME のツマミは、オシレーター1、2、3に対応しています。VOLUME のツマミの右隣には ON/OFF のスイッチが備えられ、瞬時にオフすることも可能。分厚い音作りの際には、3つのオシレーターをオンにして加工すると良いでしょう。ノイズはパーカッション的な音や風のような効果音を作る際に便利です。
3. フィルター(VCF) – 音の輪郭を整える
次にフィルターで音の表情付けをします。シンセサイザーの「音色」を作る上で、最も重要な役割を担うのがフィルターです。音の倍音構成を加工する働きがあり、Minimoog では有名な「24dBローパスフィルター」を搭載しています。高音域をカットして音を柔らかくしたり、逆に強調したりできます。フィルターには他にも、ハイパス、バンドパス、シェルフなどの種類がありますが、周波数成分をカットするということに変わりはありません。Minimoog のフィルターは、パネルの右側“MODIFIRES”の上段に用意されています。パラメーターは、
- カットオフ(Cutoff):どこから上の周波数を削るかを決める
- レゾナンス(Emphasis):カットオフ近辺の周波数を強調しピークを作る
の2つ。カットオフの12時が0で、下げていく(左回し。閉じるとも言う)とダークで柔らかな音、上げていく(右回し。開くとも言う)と、明るいサウンドになります。鍵盤を弾きながらリアルタイムに動かすだけで、いかにもシンセサイザー奏者のように音を変化させることができるはずです。このフィルターと併せて使うことでさらに表情を加えることができるのがレゾナンスです。このツマミを上げていき、フィルターのノブを下げていくと、ある時点でフィルターが自己発振します。耳で聴いて、気に入ったサウンドを作ってみましょう。こういったサウンドを生み出せるのがシンセサイザーならではの面白さです。
4. アンプ(VCA)とエンベロープ – 音の動きをつける
ピアノの音は、演奏したら自然に消えていく(減衰していく)ものですが、シンセサイザーの場合、鍵盤を押している間ずっと鳴らし続けることが可能かつ、離すとすぐに音を切ることもできます。しかしそういった音の時間的な変化を自在に操ることができるのも、シンセサイザーの特徴でもあります。機能の名前としてはエンベロープ・ジェネレーター(EG/ENV)です。エンベロープ・ジェネレーターには、ADSR という4つの設定要素があります。
- Attack(アタック):音が出てくるまでの時間
- Decay(ディケイ):最大音量から減衰する時間
- Sustain(サステイン):鍵盤を押している間の音量
- Release(リリース):鍵盤を離してから音が消えるまでの時間
Minimoog はアタック、ディケイとサステインの3つのツマミの構成となっていますが、ディケイのツマミがリリースを兼ねており(ディケイのスイッチをオンにした場合)、十分に表情のある音が作れます。フィルターのすぐ下のツマミが、フィルターにかけるEG、その下(LOUDNESS CONTOUR)が音量にかける EG です。
5. モジュレーション – 音に動きを与える
最後に、音に揺らぎを加えるモジュレーションで音の仕上げになります。Minimoog では、オシレーターやフィルターに、LFO(低周波発振器)やオシレーターなどで選択したさまざまなソースから揺らぎを加えることができます。モジュレーションを使うと、静的な音が一気に「生きている」ように感じられるのです。モジュレーション・ホイールでそのかかり具合を設定できるので、試してみましょう。
実際に音を作ってみよう
※今回は Universal Audio の Moog Minimoog ソフトシンセを使って再現をしています。
リードシンセ音(ソロ用)

- オシレーター1:ノコギリ波、レンジは4’’
- オシレーター2:矩形波、レンジは4’’
- ボリューム:オシレーター1→5、オシレーター2→2
- フィルター:カットオフ→0、レゾナンス→1.5、アマウント→3
- フィルターEG:アタック→10、ディケイ→400、サステイン→6
- アンプEG:アタック→10、ディケイ→1、サステイン→6
- モジュレーション:LFO→3(三角波)
ベース音

- オシレーター1:ノコギリ波、32’
- オシレーター2:ノコギリ波、32’
- オシレーター3:矩形波、16’
- ボリューム:オシレーター1→8、オシレーター2→2、オシレーター3→3
- ノイズ:ホワイト→1.5
- フィルター:カットオフ→-3、レゾナンス→3、アマウント→6
- フィルターEG:アタック→0、ディケイ→100、サステイン→0
- アンプEG:アタック→0、ディケイ→400、サステイン→10
- その他:グライド→3
おわりに:耳で学ぶのが一番!
Minimoog はプリセットがありません。だからこそ、「耳で音を作る力」が自然と養われます。最初は難しく感じるかもしれませんが、「ひとつのつまみを少しずつ動かして、音がどう変化するかを確かめる」ことの繰り返しが、最大の近道です。
また、Minimoog は音が太く、失敗してもどこかカッコいい音になるのが魅力。遊び心を忘れず、ぜひたくさん試して、自分だけのサウンドを見つけてください。

株式会社Core Creative代表。株式会社リットーミュージックで、キーボード・マガジン編集部、サウンド&レコーディング・マガジン編集部にて編集業務を歴任。2018年に音楽プロダクションへ転職。2021年、楽曲制作をメインに、多方面で業務を行う。2022年、事業拡大のため株式会社Core Creativeを設立。現在は東放学園音響専門学校の講師なども務め、さらなる事業拡大のため邁進中。