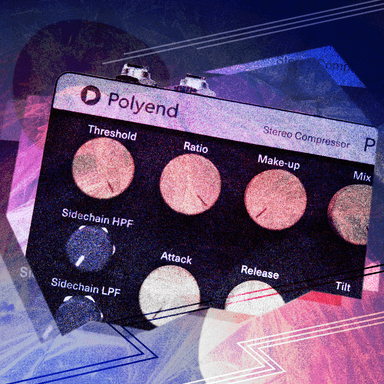制作応援キャンペーン開催中!
制作応援キャンペーン開催中!知っておきたいケーブルの前提知識
そもそもケーブルの役割って?
ケーブルは、接続した機器間で電気や電子信号の伝送を行ってくれる電線です。
例えば、携帯電話の充電器もケーブルの一種で、コンセントから携帯電話に電気を運び、電力供給を行います。
電子信号を伝送する場合、例えばパソコンから送られたオーディオ信号をヘッドホンやスピーカーに届けるといった役割を果たします。
音楽制作で使用するケーブル = オーディオケーブル
オーディオの信号の伝送を担うケーブルのことをオーディオケーブルと言います。
音楽制作で使用するような音響機器を繋ぐケーブルは、基本的にはこのオーディオケーブルと考えて良いでしょう。
アナログ or デジタル
オーディオケーブルには、大きく分けてアナログケーブルとデジタルケーブルの2種類があり、どちらを接続するかは、機器によって異なります。
アナログケーブルとデジタルケーブルの違いは、伝送する信号方式です。
アナログケーブルは、アナログ信号を伝送します。アナログ信号は、音を電気信号として変換したもので、波形として連続的に変化する数値です。
そのため、ケーブルの距離が長くなるにつれて、電気信号が劣化してしまったり、また、周辺機器の干渉によるノイズが発生しやすいので注意です。
アナログケーブルを使用する際は、長さがなるべく短いものを選択すると良いでしょう。
一方、デジタルケーブルは、デジタル信号を伝送します。
デジタル信号はアナログの音声情報を 0 と1という数値に変換し、データ化したものです。この方式では音をデータとして扱うため、信号の劣化が少なく、周辺機器の影響を受けにくいとされています。
このような特徴により、デジタルケーブルは、アナログケーブルに比べて個体差が音質に与える影響が少ないとされています。
バランス接続 or アンバランス接続
アナログケーブルには、バランス接続とアンバランス接続の2種類があります。両者の主な違いは、「ノイズに強いかどうか」です。
アンバランス接続のケーブルは、内部構造が比較的シンプルで、HOT(ホット)と呼ばれる信号を伝える線と、グランド(地面)と呼ばれる2本の線で構成されています。この構造は、外部からの干渉を受けやすく、ノイズが発生しやすいです。
一方、バランス接続のケーブルは、HOT に加えて、COLD(コールド)という信号線を持っています。この COLD は、HOT の逆相信号を伝える役割を果たし、HOT 信号と逆方向の信号を生成することで、外部からの電気ノイズを打ち消す仕組みになっています。そのため、バランス接続のケーブルは、アンバランス接続よりも比較的ノイズが入りにくいのが特徴です。

音楽制作でよく使用するアナログケーブル
XLR ケーブル(バランス)
XLR ケーブルは、アメリカのキャノン社(Cannon)によって開発されたケーブルで、別名「キャノンケーブル」とも呼ばれています。特に、マイクを接続する際に使用されることが多く、そのため「マイクケーブル」とも呼ばれています。
XLR ケーブルの特徴は、バランス伝送が可能なため、ノイズの影響を受けにくいことです。また、接続部分にはロック機構があり、ケーブルが途中で抜けることを防ぎやすく、信号の途切れや事故を防ぐために便利です。
XLR ケーブルは、マイク以外でもマイクプリアンプやスピーカーなど、音響機器同士を接続する際にも使用されます。接続方法としては、信号を受ける側にメス端子を、信号を入力する側にオス端子を接続します。

TS ケーブル(アンバランス)
TS ケーブルは、主に楽器を接続するケーブルで、別名シールドとも呼ばれています。アンバランス伝送です。
ギターやベース、シンセ、ドラムマシンなどの楽器をライン入力するなど、モノラル信号の入力時に使用します。

TRS ケーブル(バランス)
TRS ケーブルは TS ケーブルに非常に似ていますが、TS ケーブルは2本の導体を使用しているのに対し、TRS は3本の導体を使用しています。
これにより、モノラルだけでなく、ステレオ信号、そしてバランス伝送にも対応することができます。
TRS ケーブルはスピーカーとオーディオインターフェイスを繋ぐ場合に使用されてたり、DTM で使用するヘッドフォンのジャックに採用されたりしています。
初歩的なことですが、ヘッドホンが片方からしか音声が流れていない場合は、このジャックがしっかり刺さっていないことが多いです。しっかりジャックが刺さっているかを確認しましょう。

RCA ケーブル (アンバランス)
RCA ケーブルは、音声や映像機器で一般的に使用されるケーブルです。
この RAC の設計をしたRadio Corporation of America という会社の頭文字から「RCA」と呼ばれています。
RCA ケーブルは、通常2本または3本のケーブルから構成されており、色分けがされています。一般的に、白色は左(L)音声、赤色は右(R)音声、そして黄色は映像の信号伝送を担当しています。
使用用途としては DJ ミキサーにターンテーブルを接続する際や、DA コンバーターに使用されます。
音楽制作でよく使用するデジタルケーブル
MIDI ケーブル
MIDI ケーブルとは、MIDI の伝送を担うケーブルのことです。
MIDI とは、演奏情報のことです。たとえば、ピアノの鍵盤を押すタイミング、押した場所、押してから話すまでの時間、押したときの強さなどです。このような情報をデータ化し MIDI 情報として扱うことができます。
MIDI ケーブルを使用することで、電子楽器を MIDI コントローラーとして扱えたり、電子楽器同士を MIDI ケーブルでつなげて同時演奏をすることも可能です。
USB ケーブル
USBケーブル はオーディオインターフェースとパソコン、MIDI キーボードとパソコンなど、様々なデジタルデータの伝送を行います。
USB は比較的新しい規格のため、古い機材では使用できないこともあるので注意です。
また、USBケーブルと一括りに呼んでも、TypeA、TypeB、TypeC、Miniなど様々な端子の形状があります。

S/PDIF ケーブル
S/PDIF ケーブルは SONY と Philips が共同開発した規格で、正式名称は「Sony/Philips digital interface」です。
このケーブルは、デジタル音声信号の伝送を担っており、ノイズの混入が少なく、 1本で複数のチャンネルの信号を送信できるというメリットがあります。
元々、プロの現場で業務用に使用されていた AES/EBU 規格があり、これを一般家庭でも使用できるように簡略化して作られたのが S/PDIF ケーブルです。
利用用途としては、オーディオインターフェイスの入力数を増やす場合などで使用します。
S/PDIF ケーブルに採用されている端子は、光デジタル音声端子(オプティカル)型と同軸ディジタル音声端子の2種類あります。
さらに、S/PDIF と同様にオプティカルを採用したケーブルに、ADAT オプティカルがあります。
しかし、ADAT オプティカルと S/PDIF は、伝送する信号が違うため、互換性はありません。
ADAT オプティカルの利用用途も、オーディオインターフェイスのインプット数を増やす際に使用されることが多いです。
S/PDIF ケーブルを選択する際は端子による違いや、ADAT と間違えやすいので注意です。
機器によっての違い
変換ケーブルの使用
音楽制作でケーブルを使用する際、音声信号を送る機器(送り元)と、信号を受け取る機器(送り先)があると思いますが、これらの機器の接続端子が異なる場合があります。そのような場合、両端の端子が異なるような、変換ケーブルを使用すると良いでしょう。
例えば、スピーカーをオーディオインターフェースに接続する際、オーディオインターフェースのアウトプット(OUT)がフォーン端子で、スピーカー側の INPUT が XLR 端子の場合があります。このような場合、XLR-TRS 端子のケーブルを使用すると適切に接続できます。実際に筆者が使用しているスピーカーはこのように接続しています。
コンボジャックとは
コンボジャックとは、XLR 端子とフォーン端子の両方に対応するもので、最近のオーディオインターフェースに採用されていることが多いです。

TS と TRS の違い
TS ケーブルと TRS ケーブルの違いは、端子の形状を見れば判断できますが、メス側(差し込み口)では見た目だけでは区別がつかないことがあります。
どちらを用意した方がいいか分からない場合は、機材の取扱説明書を確認して、バランス接続かアンバランス接続かを確かめましょう。
機材によっては、BALANCE(バランス接続)や UNBALANCE(アンバランス接続)という表記がされていることがあります。BALANCE と記載されていれば TRS ケ ーブルを、UNBALANCE と記載されていれば TS ケーブルを用意すれば良いでしょう。
一般的には、ギターなどの楽器を直接繋ぐ場合は TS ケーブル、シンセサイザーやキーボードなどの場合は TRS ケーブルを使用する場合が多いです。
ちなみに、バランス接続に TS ケーブルを使用しても問題はありませんが、その場合、アンバランス接続として機能します。同様に、アンバランス接続に TRS ケーブルを使用しても、アンバランス接続として動作します。
ケーブルで音は変わる?
結論からお伝えすると、ケーブルで音質は変わると言われています。
ケーブルは導体となっている電流や信号を伝える役割をになっている内部導体(芯線)という部分、それを包み込むように電気が漏れたり短絡(ショート)したりするのを防ぐ絶縁体、そしてる外部からの電磁波やノイズの干渉を防ぐための外部導体(シールド)と呼ばれる部分、さらにこれらを覆う外部被覆(ジャケット)があります。
これらの材質の違いや、大きさ、採用している構造の違い、設計の違い...などなど。
このような物理的な違いは、多かれ少なかれ音に影響を与えます。
特にアナログケーブルでは、先にお伝えしたように、ケーブルの長さが長い程電子信号の劣化が起こりやすいので、なるべく短いものを選ぶと良いです。
ケーブルを品質の良いものに変えても、人によっては判断が付かないこともありますが、多くのエンジニアやミュージシャンの方がケーブルにこだわって選択し、さらには自作をしている人がいるのも事実です。
特にギターやベースなどの楽器は比較的顕著に音が変わりやすいので、ケーブルによる音の聴き比べを試してみるのも良いでしょう。

まとめ
以上、今回は音楽制作で使用する、ケーブルの種類についてご紹介しました。
まだまだ紹介しきれなかったものもありますが、今回ご紹介したようなケーブルの基礎知識を知っておくだけでも、最適なケーブルを選びがスムーズになるでしょう。
ONLIVE Studio にご登録いただいている、40年以上の経験を持つベテランエンジニア天童淳さんにインタビューした際、スタジオに入る際にはケーブルをある程度持ち込んだり、引き回しの順番があるとお話していました。
ぜひ合わせて見てみてください。
他にも、ONLIVE Studio にご登録いただいている STUDIO SONIC TEST では、再生環境の向上のため、ケーブル制作も行っているとのこと。
ご興味のある方は一読し、お問い合わせしてみるのも良いでしょう。


東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。