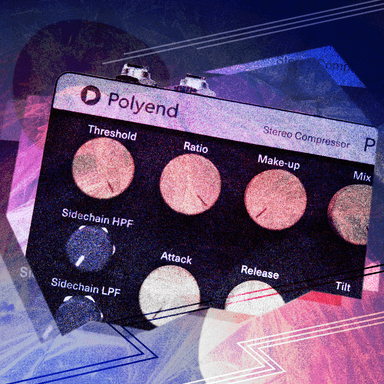制作応援キャンペーン開催中!
制作応援キャンペーン開催中!楽曲を構成する要素
まずは楽曲を構成する要素を見てみましょう。
ちなみに、Aメロ、Bメロ、サビなどは日本独自の呼び方です。この章では、英語での表記の仕方と合わせて解説していきす。
※「Aメロ≒Verse」のようなイメージで、日本語と英語の考え方は完全に同じ意味ではありません。しかし、多くの場合では Aメロが指すものは Verse、Bメロを指すものはと Pre chorus 捉えて問題ないでしょう。
Intro(前奏)
曲の冒頭に挿入される、歌が始まる前のセクションです。
Verse(Aメロ)
物語で例えると序章部分であり、Intro の後に挿入される場合が多いセクションです。
Pre chorus(Bメロ)
Verse とは違うメロディーの、Chorus の前に挿入されるセクションです。
Chorus(サビ)
曲の主役的存在を担うセクションです。
通常は1曲を通して2回以上繰り返され、一番伝えたい歌詞がサビにくることが多いです。
Post Chorus(ポストコーラス)
Chorus の後に繰り返されるセクションです。
Chorus とは違うメロディーですが、Chorus の延長線上にあります。
Interlude(間奏)
曲の途中に挿入されるセクションです。楽器のみで演奏されることが多いです。
Bridge(Cメロ)
Verse や Pre chorus とは違うメロディのセクションです。2番の Chorus の次に入ることが多く、ラストの Chorus の前に緊張感を持たせる役割があります。
Outro(後奏)
楽曲の最後の部分。
Refrain(リフレイン)
繰り返されるフレーズのこと。
実は色々ある、曲構成の形式
Verse - Chorus
Verse - Chorus という順番で進んでいく曲構成です。
現代の楽曲で頻繁に使用される構成の一つです。
Avril Lavigne『Sk8er Boi』
Verse - Pre chorus - Chorus
先ほどの Verse - Chorus 形式の前に、Pre chorus を挿入した構成です。
あいみょん『マリーゴールド』
AAA 形式(Strophic)
AAA 形式は、一つのセクションで構成されている楽曲です。
このような形式は合唱曲や民謡などでよく見られます。
『Amazing Grace』
ABAB形式
対照的な2つのセクションによって構成されている形式です。
1950〜60年のロックンロールやロックでよく使われています。
Elvis Presley『Jailhouse Rock』
32小節形式 (AABA 形式)
20世紀前半に主流だった形式です。
1900〜1950年頃流行していたジャズスタンダード曲や、ミュージカル曲などでよく見られます。
このような形式は通常、8小節 × 4=32小節で構成されており、AABA という形式になっています。
明確な Verse や Chorus がない形式で、A というセクション、B というセクションに分けることができます。(ここでの A や B は、A メロや B メロとは関係ありません。)
The Wizard of Oz『Somewhere Over the Rainbow』
12小節ブルース
この形式は、ブルースやジャズなどで用いられる曲構成です。
この形式の場合、コード進行は基本的には決まっており、I7 と IV7、V7 が用いられます。
4小節×3=12小節で構成され、AA'B 形式とも捉えることができ、歌詞は A を2回繰り返し、B で締めます。
James Brown『I Got You (I Feel Good)』
現代の王道パターンと変わりゆく構成トレンド
J-POP の王道「落ちサビ」
この構成は、J-POP の王道パターンとも呼べるでしょう。
「落ちサビ」とは、サビのオケ(伴奏)を控えめにして、歌をしっとりと聴かせる、最後のサビの前に挿入されるセクションのことです。
この構成は、YUI『Good-bye days』、絢香『おかえり』など、特に2000年代のヒット曲に多い印象です。
とはいえ今でも根強い人気があり、2018年にリリースされたあいみょんの『マリーゴールド』や、昨年(2024年)のヒット曲、tuki.『晩餐歌』にもこのような構成が採用されています。
また、洋楽でももちろんよく使われる構成の一つです。昨年ヒットした Teddy Swims『Lose Control』もこのような形式をとっていました。
イントロや間奏、アウトロの長さ
ストリーミング時代になり全体の傾向として、イントロや間奏、アウトロの長さは短くなったといわれています。
CD が主流だった時代は、曲を聴くためには CD を購入する必要がありましたが、ストリーミングの時代ではいかに冒頭でリスナーを引きつけ、離脱を防ぐか がより重要になっています。
たとえば、全世界でヒットした BTS『Dynamite』 は、イントロや間奏、アウトロがほぼなく、常に歌が入っている構成になっています。
このような曲の作り方は、現代の音楽市場の傾向を反映していると言えるでしょうか。
王道から脱却!曲構成をご紹介
※この章の内容は、楽曲構成について筆者が独自に分析したものであり、アーティストや制作陣の意図と異なる場合があります。
DREAMS COME TRUE 『またね』
Aメロ - Bメロ - サビ - Aメロ - Bメロ - サビ - 間奏 - Bメロ - サビ - アウトロという構成になっており、Bメロ -サビの流れが3回繰り返されます。
また、1回目と2回目のサビはほぼ同じですが、3回目のサビはそれまでのサビの雰囲気を受け継ぎながらも、若干違うメロディーと歌詞になっています。
YOASOBI『アイドル』
Cメロに近いメロディー - Aメロ - Bメロ - サビ - ポストコーラス - Aメロ(Cメロに近い+全く異なるセクション) - サビ - ポストコーラス(1番と若干違う)Cメロ - Bメロ - コーラス - ポストコーラスという構成になっています。
Cメロから始まる斬新な構成(Cメロと位置付けて良いかも悩みますが...)、また、同じポストコーラスでも少しづつメロディーも異なっていたり、2回目の Cメロはハーフテンポになっていたり...と、次々の展開が面白いです。
松任谷由実『中央フリーウェイ』
Aメロ - サビ - Aメロ - 間奏 - Aメロ - サビ - Aメロという構成。
2番の Aメロが終わった後、間奏を挟んでまたAメロを続けるパターンです。
Taylor Swift 『Cruel Summer』
Intro - Verse - Pre chorus - Chorus - Verse - Pre chorus - Chorus - Bridge - Chorus - Bridge ...となっており、楽曲の中で Bridge が2回出てきます。
BTS (방탄소년단) 『 'FAKE LOVE'』
歌い出しの部分のセクションが、1番のPre chorus の前、そして曲の一番最後に登場し、位置付けが難しいセクションとなっています。
Spice Girls 『Wannabe』
Pre chorus から始まるという斬新な構成です。
Mariah Carey 『All I Want For Christmas Is You』
クリスマスの大定番曲。
1994年にリリースされて以降長年愛されており、今でもクリスマスの時期になると街やお店など、どこかしらで耳にしますよね。
この曲はどこが Verse で、どこが Chorus なのかが明確ではありません。
Journey『Don't Stop Believin』
どこを Chorus と捉えるかは難しいですが、一番曲が盛り上がり、曲名にもなっている「Don't Stop Believin〜」というワードで歌うセクションは、3分20秒あたりまででてきません。このセクションを Chorus と捉えた場合、Chorus がかなり後半まででてこない、またOutro と捉えた場合でも Outro が一番盛り上がるという面白い構成です。
Billie Eilish『Happier Than Ever』
この曲は大きく分けて2つのセクションに分けることができます。
前半はしっとり始まるレトロな雰囲気で、32小節形式のような構成になっています。後半に入ると、Verse -Chorus の構成に近いものになっています。
また、曲調も前半と後半では対象的になっており、後半は特に激しいロック調になり、音割れもバリバリと面白い音作りです。拍子も4/4拍子から6/8拍子になります。
まとめ
以上、今回は曲の構成についてご紹介しました。
改めて構成に着目してみると、実にさまざまなパターンがあることが分かります。長年聴いていた曲でも、「こんな構成になっていたんだ!」という新たな発見があるかもしれません。
また、ジャンルや年代、邦楽と洋楽の違いなどを分析してみると、それぞれの王道パターンや面白い傾向が見えてくることもあります。
一方で、曲の構成を正確に判断するのは難しく、明確な正解がない場合も多いものです。だからこそ、自分なりに分析をしてみることで、新しい視点が生まれるかもしれません。
さらに、現代の主流の構成を参考にするだけでなく、ときには変化球の構成を取り入れてオリジナル曲を作ってみるのも面白いですね。
ぜひ、さまざまな構成を意識しながら、音楽制作を楽しんでみてください!
ONLIVE Studio では、音楽のプロフェッショナルに依頼ができます。
音楽制作でお困りの方は、是非ご活用ください!

東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。